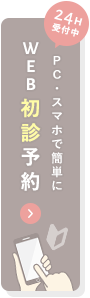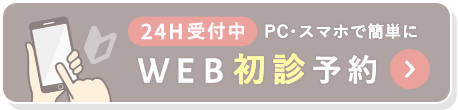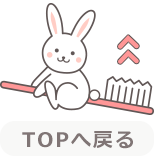Sleep apnea syndrome
いびき・睡眠時無呼吸症候群
健康で充実した毎日を過ごすために、睡眠は非常に重要な役割を担っています。
パートナーがいる場合は、個人だけの問題だけではなく、
一緒にいるパートナーの健康を害することにもなってしまう可能性もあります。
快適な睡眠の妨げになる「いびき」「睡眠時無呼吸症候群」に対して、
適切な治療を行い症状の改善を図ってまいります。
あなたは いびき をかいていませんか?
大きな「いびき」や特に呼吸が止まる「いびき」は要注意なのです!!
その いびき は睡眠時無呼吸症候群かもしれません。
最近話題となっている『睡眠時無呼吸症候群』は、夜間睡眠中に10秒以上呼吸が
一時停止すること(無呼吸)が7時間中30回以上、または1時間中5回以上起こる病気です。
こんな症状がある場合には、ご相談ください。
- 朝の目覚めが悪い。何時間寝てもどうも頭がすっきりしない。熟睡感が無い。
- 朝起きたときに頭痛がする。
- 日中に眠気がある。会議中、パソコン、運転、テレビを見ているときなど。
- 夜中にトイレに起きる回数が多い。
- 何となく夜の生活から遠ざかっている。
- 肥満があり、よくいびきをかく。
- 睡眠中、呼吸がとまり、呼吸が再開するときに大きないびきをかく。
- 夜中によく目が覚めてしまう。
- 大きないびきをかいている。
いびきと睡眠時無呼吸症候群
| いびき |
いびきが発生する場はのど(上気道)です。肥満や飲酒、老化その他の原因で舌根が落ち込んで狭くなったのどに無理やり空気を通そうとするといびきが生じます。いびきをかく事自体は病気ではありませんが、呼吸がしづらくなっている状態といえます。
|
| 睡眠時無呼吸症候群 |
睡眠時無呼吸は、のど=上気道=空気の通り道が完全に詰まってしまうことで生じます。いびきといびきの間にまるで呼吸がとまってしまうようないびきをかく人は『睡眠時無呼吸症候群』の可能性があります。
治療をせずに放置しておくと、高血圧リスク2倍、動脈硬化、不整脈、狭心症、心筋梗塞などリスク3倍3倍、脳梗塞などリスク4倍、交通事故リスク7倍、ED(勃起障害)など生命に危険が及ぶ場合もあります。適正な症状分析と診断、治療、予防などの対策が必要になります。
眠っている間に呼吸が数十回、ときには数百回と止まるようであれば、体内の酸素不足が深刻になってくるでしょう。また、無呼吸によって夜間に充分な睡眠がとれないため、昼間に強い眠気が起こり日常生活に支障をきたすだけでなく、放置しておくと合併症が併発する場合もあり早期に適切な治療を行うことが大切です。
|
いびき・睡眠時無呼吸症候群の原因
いびき・OSASの原因は下記の12項目があげられます。
• 肥満
• 仰向け(上向)で寝る
• あごが小さい(噛み合わせが悪い)
• 咽頭扁桃、口蓋垂(のどちんこ)の肥大
• アルコール(飲酒)
• 老化(加齢)
• 口呼吸
• 鼻の疾患
• 舌の肥大
• 疲労(ストレス)肉体的疲労
• 薬(睡眠薬・精神安定剤)
• 室内(寝室)の気温や湿度
治療の流れ
- 1カウンセリング
- いびきに関して詳しくお聞きします。

- 2検査
- 治療用マウスピース製作のため、口の中の診査を行います。

- 3レントゲン検査
- レントゲンで状態を調べます。

- 4型取り・模型作成
- 歯形をとり、模型を製作します。

- 5治療開始
- 治療用マウスピースによる治療を開始します。